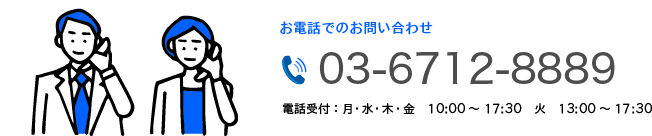毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です
[厚生労働省]からの「お知らせ」です。
厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死や過重労働による健康障害を防ぐための取り組みを全国で展開しています。
この月間では、国民の理解と関心を深めることを目的に、シンポジウムの開催、ポスターやパンフレットによる啓発、長時間労働の是正を目指す「過重労働解消キャンペーン」などが実施されます。働く人々の命と健康を守るため、社会全体で過労死等の防止に取り組むことが求められています。
<事主の取組>労働者の方々が相談しやすい環境づくりが必要です。
<労働者の取組>心身の不調に気づいたら、周囲の人や専門家に相談を。
過労死等とその防止への理解を深めましょう。
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその防止に対する理解を深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。
【過労死等防止のための取組】
- ◎長時間労働の削減
- ◎過重労働による健康障害の防止
- ◎働き方の見直し
- ◎職場におけるメンタルヘルス対策の推進
- ◎職場のハラスメントの予防・解決
- ◎相談体制の整備等
過労死等とは?
業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。
<事主の取組>
長時間労働の削減に向けて、事業主が取り組むべきことは?
労働者の労働時間を正確に把握しましょう。
時間外・休日労働協定(36協定)の内容を労働者に周知し、週労働時間が60時間以上の労働者をなくすよう努めましょう。
「労働時間適正把握ガイドライン」で詳しく解説しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
<事主の取組> <労働者の取組>
働きすぎによる健康障害を防止するために必要なことは?
事業主は労働者の健康づくりに向け積極的に支援すること、労働者は自らの健康管理に努めることが必要です。
<事主の取組> <労働者の取組>
働き方はどのように見直せばよいですか?
事業主はワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境づくりを推進しましょう。
使用者と労働者で話し合って計画的な年次有給休暇の取得などに取り組みましょう。
<事主の取組> <労働者の取組>
勤務間インターバル制度とは?
勤務間インターバル制度は、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために有効なものです。
労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。
勤務間インターバル制度導入がもたらすメリット
勤務間インターバル制度を導入することによって、事業主、従業員双方に以下のようなメリットが期待されます。
メリット1 ▶ 従業員の健康の維持・向上につながります。
インターバル時間が短くなるにつれてストレス反応が高くなるほか、起床時疲労感が残ることが研究結果から明らかになっています。 十分なインターバル時間の確保が、従業員の健康の維持・向上につながります。
メリット2 ▶ 従業員の定着や確保が期待できます。
労働力人口が減少するなか、人材の確保・定着は、重要な経営課題になっています。十分なインターバル時間の確保により、ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることは、職場環境の改善等の魅力ある職場づくりの実現につながり、人材の確保・定着、さらには、離職者の減少も期待されます。
メリット3 ▶ 生産性の向上につながります。
十分なインターバル時間の確保は、仕事に集中する時間とプライベートに集中する時間のメリハリをつけることができるようになります。このため、仕事への集中度が高まり、製品・サービスの品質水準が向上するのみならず、生産性の向上にも期待できます。
<事主の取組> <労働者の取組>
心の健康を保つために取り組むべきことは?
事業主はメンタルヘルス対策を積極的に推進し、労働者はストレスチェックにより、自身のストレスの状況に気づき、セルフケアに努めましょう。
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
ストレスチェックの企業向けの相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」
0570-031050(平日10時~17時 土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
<事主の取組> <労働者の取組>
職場のハラスメントの防止に向けて取り組むべきことは?
事業主は、予防から再発防止に至るまでの一連の防止対策に取り組み、職場のハラスメントを防止する必要があります。
労働者とその周囲の方は、ハラスメントに気づいたら相談窓口へ連絡しましょう。
2022年4月から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が中小企業を含む全ての企業の義務となりました。
●ハラスメント対策について厚生労働省HPで詳しく解説しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
●ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」もご活用ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
<事主の取組> <労働者の取組>
新しい働き方を導入する場合はどのように対応すべき?
企業も労働者も安心して取り組むことができる環境を整備することが重要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000770194.xlsx
https://www.mhlw.go.jp/content/000770193.xlsx
<事主の取組> <労働者の取組>
労働者が過労死等の危険を感じた場合に備えて取り組むべき対策は?
労働者は周囲の人や専門家に早めに相談をしましょう。
事業主は労働者が相談に行きやすい環境作りが必要です。